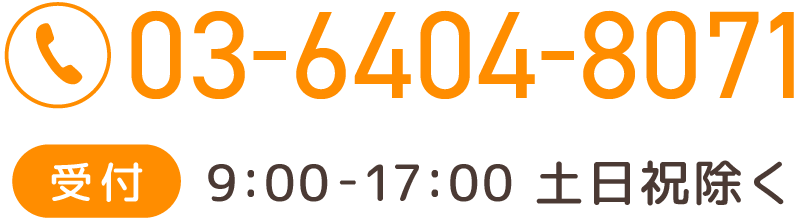Smart Marcheトピックス詳細
【離職率改善】福利厚生が鍵!社員が定着する職場づくりのポイント
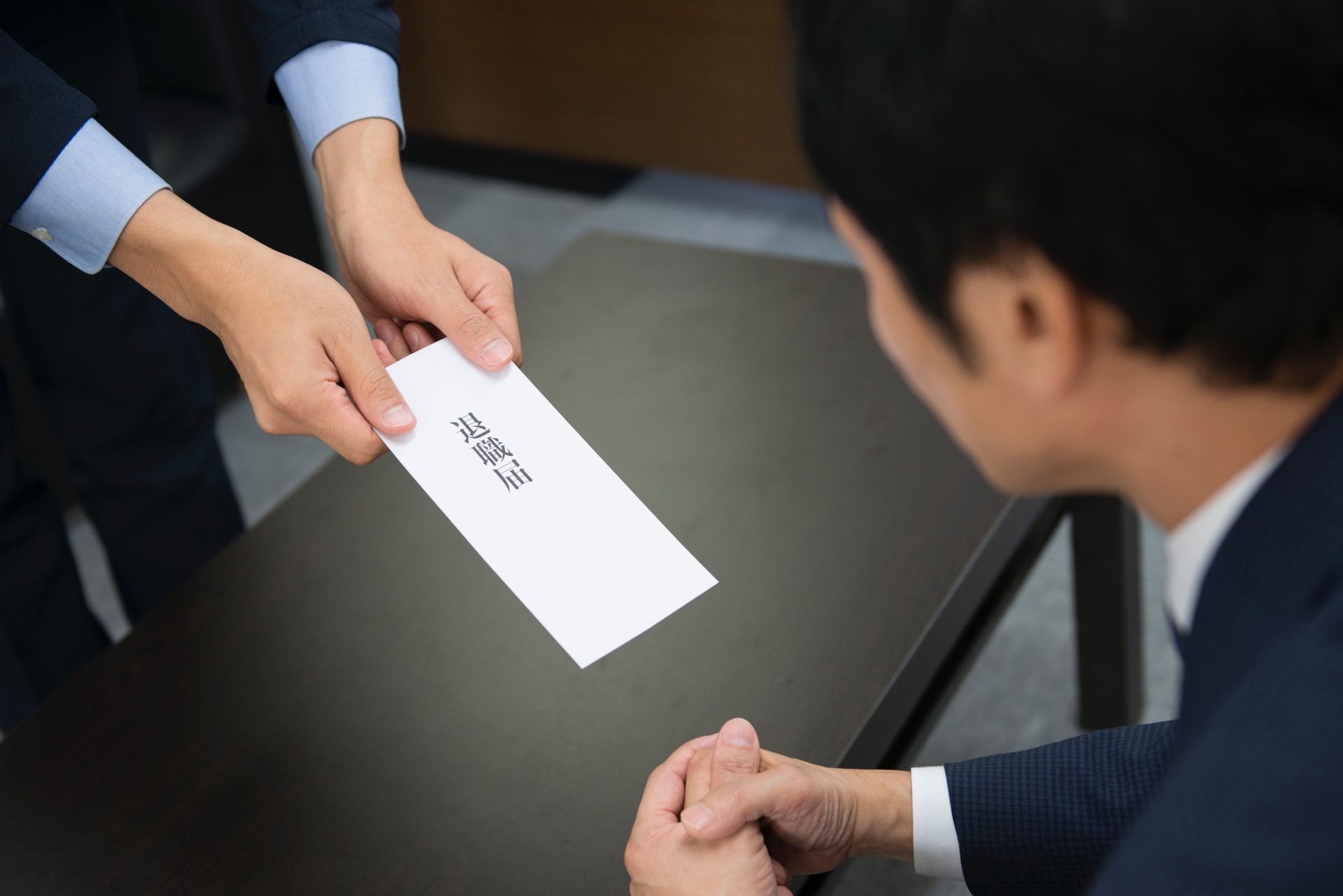
「また人が辞めてしまった…」
多くの企業が抱える、この切実な悩み。
離職は企業にとって単なる人の入れ替わりではありません。
採用コスト、新人教育のコスト、そして何より生産性の低下という大きな負担を企業に与えます。
こうした影響を数値で客観的に把握するために用いられるのが『離職率』です。
離職に関する自分の職場はどうなのか、ということを客観的に見ることができるこの指標を、まずは正しく理解しておくことが重要です。
離職率とは
離職率とは、ある期間内にどれだけの社員が離職したかを示す指標です。
厚生労働省の「雇用動向調査」では、離職率は以下のように定義されています。
離職率 = 「常用労働者」数に対する離職者数の割合
「常用労働者」とは、
- 期間の定めがない雇用者(無期)
- 1カ月以上の期間を定めて雇用されている者(有期)
のいずれかに該当する労働者を指します。
調査期間中に事業所を退職・解雇された者を指し、出向者や出向からの復帰者を含む一方で、同一企業内の他の事業所へ移動した者は含まれません。
厚生労働省「雇用動向調査」
https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/9-23-1b.html
計算方法
厚生労働省の雇用動向調査では、下記の算式が使われます
- 離職率 = 離職者数 ÷ 1月1日現在の常用労働者数 × 100(%)
具体例
- 例1:1月1日時点の常用労働者数が1,000人、年間の離職者が50人 → 離職率は 5% (50 ÷ 1000 x 100 =5)
- 例2:社員数200名で4名が退職した場合 → 離職率は 2% (4 ÷ 200 × 100=2)

離職率の今
厚生労働省が公表した令和5年のデータによると、新規大学卒就職者の就職後3年以内の離職率は34.9%、新規高卒就職者は38.4%となっています。
つまり、新卒で入社した社員の約3人に1人以上が3年以内に離職している計算になります。
新規学卒者の離職状況 – 厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000137940.html
新規学卒就職者の離職状況(令和3年3月卒業者)を公表します
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000177553_00007.html
離職率が改善されない企業の課題
離職率が高い企業には、いくつかの共通した課題が見られます。
採用時の情報不足やミスマッチ
求職者に対して実際の業務内容や職場環境が十分に伝わっておらず、入社後に「思っていた仕事と違う」というギャップが生まれるケースです。
長時間労働・休暇制度の形骸化
制度上は有給取得が可能でも、実際には取りにくい、定時で帰りにくい雰囲気が大変強いなど、働き方の改善が進んでいない状況です。
社員同士の交流不足
リモートワークが普及した今、社員同士が直接顔を合わせる機会が減り、会社や組織とのつながりを感じにくくなっています。
福利厚生が形式的で、社員に実感されていない
制度は整備されているものの、実際に利用しやすい環境が整っていない、または社員のニーズと合っていない場合です。
福利厚生が定着率に与える影響
福利厚生は、単なる「待遇」ではなく、社員が日々の仕事を通じて「働きやすさ」を実感するためのものです。特に、日常的に触れる機会の多い施策ほど、社員の満足度に直接影響を与えます。
「定着率」とは、「入社した社員が一定期間後も会社にとどまり続けている割合」を指します。
福利厚生が充実している会社ほど、社員が長く働き続けやすくなり、結果的に定着率の向上につながることが多いです。
充実した福利厚生制度があること自体も重要ですが、さらに重要なのは、その制度が「いかに使いやすいか」です。
例えば、申請手続きが煩雑だったり、利用することに心理的な障壁があったりすると、せっかくの制度もその効果を十分に発揮できません。
福利厚生見直しのポイント
福利厚生の改善を検討する際は、以下のポイントを意識することが大切です。
「コスト」ではなく「投資」として捉える
福利厚生にかかる費用を単なるコストと見るのではなく、社員の定着率向上や生産性向上につながる投資として位置づけることが重要です。
\ 関連してこちらも読まれています /
会社やオフィスに設置する無人コンビニはコスト?それとも投資?
自社に合った施策を選び、段階的に導入する
他社の成功事例をそのまま真似るのではなく、自社の社員の特性や課題に合わせた施策を選択し、無理のない範囲で段階的に導入していくことが成功の鍵です。
社員の声を定期的に収集し、改善を続ける
一度導入した制度で終わりではなく、定期的に社員の意見を聞き、より良い制度に改善し続ける姿勢が大切です。
離職率を下げるための福利厚生サービスとは

離職率を改善するためには、社員が「この会社で働きたい」と心から思えるような、働きやすさを実感できる福利厚生が欠かせません。
制度を整えるだけでなく、社員の「日常」に寄り添い、手軽に利用できる工夫が、定着率を大きく左右します。
次の離職率改善の一手として、「毎日いつでも利用できる福利厚生サービス」を検討する価値は十分にあるでしょう。
\ 日常的に利用できる福利厚生についてこちらも読まれています /
オフィスに無人コンビニがあると、こんなに変わる!スマートマルシェが支える1日のリアル
社員の日常に寄り添い、手軽に利用できる福利厚生として、オフィスコンビニの導入を検討してみませんか。
スマートマルシェはオフィスコンビニのパイオニアです!お気軽にご相談ください!